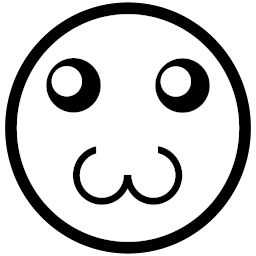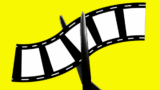ゲームは『コスパは良い』が『タイパは悪い』趣味になりつつある

あなたはゲームを遊びますか? 私はゲーマーなので、これまで数々のゲームを遊んできました。今や娯楽産業の中でもゲーム産業は映画産業と音楽産業を足した市場規模よりも大きくなりエンタメの中心と言える産業になりました。
そんなエンタメの中心となり、年々市場拡大と成長を続けていると言われていたゲーム業界ですが、ここ数年で成長が鈍化(ソース)しているようです。コロナ禍による巣ごもり需要終了後、ゲーム市場は成長率が低下しています。
半導体不足によるゲーム機やパソコンの価格高騰、インフレや人件費上昇による開発費の高騰など、これらの一時的な要因も考えられますが、ゲーマーの私はゲーム産業が生み出しているゲームそのものに問題があると考えています。
当ブログはAI学習禁止(無断使用禁止)です。
大作ゲームのコスパ&タイムパフォーマンス問題
大作ゲームを作ることが大きなリスクに
今のゲーム業界で大きな話題になりやすいのは主に欧米が中心となって作る「AAAタイトル」と言われる、巨額な予算が投じられる大規模なゲームです。
ここ10年以上、コンシューマー向けゲーム業界は「AAAタイトル」が中心となり、市場を牽引してきました。しかし、近年その「AAAタイトル」が生み出す収益に限りが見られています。
AAAタイトルの開発費が収益の成長を上回るペースで増加していることも指摘され,2017年から2022年にかけてのCAGRは6%だったが,2022年から2028年にかけてのCAGRは8%になる見通しだという。
―― ボストン コンサルティング グループ,ゲーム業界に関するレポートを公開。日本のゲームへの支払い意思額は世界平均を下回る より
その原因として考えられるのが開発費の高騰です。開発費と一緒に収益も上がっていれば問題ありませんが実情はそうなっていません。その結果、開発費の上昇が収益を圧迫し、利益を上げることが難しくなっています。
また、開発費の増大が開発者のリストラ(レイオフ)へと繋がり、2023~24年は欧米のゲーム業界を中心に大規模なリストラが行われました。
なおGame Industry Layoffsでは、2022年は合計8500人、2023年には合計1万500人の失職者が出たと推計されている。今年は本稿執筆時点で1万4600人と推計されており、昨年を大きく上回る失職者を出すかたちとなった。
―― ゲーム業界では2024年、失職者が「1万4000人以上」発生したとの報告。2年連続増、スタジオ規模問わずレイオフの波は続く – AUTOMATON より
それでも完成した「AAAタイトル」が評価され、大ヒットしているのであれば将来の展望が開けますが、そうはなっていません。ゲーマーであれば「AAAタイトル」が近年大コケしまくっている光景を目の当たりにしているでしょう。
昨年のThe Game Awards 2024ではGame of the Yearのノミネート作品に欧米の「AAAタイトル」が含まれませんでした。作品の評価も芳しくありません。欧米の「AAAタイトル」及び大手スタジオともに陰りが見られます。
評価や売上だけが問題ではありません。「AAAタイトル」のような大作ゲームは開発が長期化しており、開発期間に4~5年かかるのが当たり前になっています。ものによっては10年近くかかっているものもあります。
例えば、Ubisoft の『スカル アンド ボーンズ』には約10年の開発期間がかかっています。Firewalk Studiosが制作、ソニーが世に送り出した「CONCORD(コンコード)」開発は8年かかっています。どちらも大コケしました。
開発の長期化にとって問題となるのは業界のトレンドや売り時を逃してしまうことです。ゲームが完成したときには同じジャンルのゲームが飽きられていたり、競合となるゲームが多数あったり、誰も注目していなかったりします。
また大作ゲームの開発費の増大が予算の確保のために投資家の意向を組まなければならず、その影響で「DEI」や「NFT」など投資家受けはするがゲーマーは別に求めていないものをゲームに取り入れなくてはならなくなりました。
その結果、NFTゲームの大半がサービス終了し、DEI要素が強いゲームは売上に問題を抱えることになりました。消費者ではなく投資家の方を向いてゲームを作っているんだからそうなるよねと多くのゲーマーが思ったことでしょう。
こういった理由で大作ゲームは開発規模が大きくなった結果、ゲームを作るリスクが増大し、そして開発者は自由にゲームを作れなくなりました。
圧倒的に時間が足りない最近の消費者
ここまでは開発者側やゲームを売る側の視点で話をしてきましたが、ここからは消費者目線でも話をしていきます。つまりゲームをやる側の視点ですね。
先ほど話に出た「AAAタイトル」が欧米ゲーム業界の主流になったのは2012年頃。もっと前から言えば、TVゲームがボリュームを重視し始めたのはPS2世代辺りからです。
ゲームは年々ボリュームが増大し、大手パブリッシャーが出すゲームは攻略が10時間では終わらないようなゲームが普通になってきました。ですが、ゲーマーは比較的長く遊べるゲームに関しては寛容でした。
大手が作る大作ゲームは攻略に50~100時間の時間がかかるようになり、長く遊べるゲームは「スルメゲー」や「時間が溶けるゲーム」と言われるようになりました。
ゲームは1つあたりの単価は高いですが、金銭的なコストパフォーマンスだけで考えると、ゲームは映画や音楽よりも遥かに長く時間を潰せるコンテンツと言えるようになりました。同様の主張はゲーム開発者の桜井氏もしています。
しかし今は金銭的なコスパだけでなく、タイパ(タイムパフォーマンス)も求められる時代。動画の倍速視聴やながら見、ニュースの要約、切り抜き動画など、時間をなるべく無駄にしないコンテンツが流行しだすようになりました。
コンテンツの内容自体にも変化が現れ、音楽で言えばイントロの時間が減り、いきなりサビから入る楽曲が流行るようになりました。カラオケのJOYSOUNDがサビだけを歌える「サビカラ」を提供しだしたのもその影響です。
正直言って私のような長年のゲーマーからすると「タイパ」重視の考えはコンテンツの楽しみ方そのものを毀損する行為だと思うのですが、デジタルネイティブと呼ばれるZ世代では考え方が異なります。
物心がついた頃からデジタル機器が身近にあった世代では、日々ネットを通じて大量の情報とコンテンツに触れることが日常となっています。
デジタルネイティブはYouTubeやTVerのようなAVOD(広告収益型動画配信)やNetflixやプライムビデオのようなSVOD(定額制動画配信)、SNSなどを通じて大量の情報とコンテンツを日々ほとんど無料で消費しています。
こういったコンテンツの消費の仕方をしていると、一つ一つのコンテンツをしっかりと味わうといった感覚は希薄になり、つまらなかったら即座に次のコンテンツに移るというタイパ重視の考えになってしまうことは仕方ありません。
かくいう私もクリアに100時間以上かかるゲームを遊んでいる時に100時間もあったら2時間の映画が50本見れるなぁと考えてしまうことがあります。それを考えると大作ゲームはタイパの悪い商品と言えるでしょう。
テレビが世の中の話題の中心だった時代とは異なり、現代は人と共通の話題を探すのが難しい時代。同じ時間を使うなら、他人との話題作りのために、なるべく多くのコンテンツや話題に触れたいと考えるのは自然な流れです。
音楽の聴き放題サービス、映画やドラマの見放題サービスのサブスクを消費しているだけでも時間が足りないと感じることが多い今日このごろ、クリアまでに時間がかかるゲームは敬遠されることになるのは避けられないでしょう。
ゲーム業界全体が変わらない限り受難は続く
以上が、ゲームは『コスパは良い』が『タイパは悪い』コンテンツになりつつあるという私の主張です。正直ゲーマーである自分がこのような主張をしているのは矛盾している気がしますが、実感があるので文章に起こしてみました。
これから先、大作ゲームは市場から敬遠されるかもしれませんが、個人や少人数のチームが制作するインディーズゲームは盛り上がっています。作る側は大作ゲームを作ることに拘らず、市場の変化を受け入れるべきだと思います。
ゲーム業界は長年様々な変化があった業界なので、これから先もその変化に合わせてコンテンツも変わっていくことになるでしょう。不安もありますが、今までになかったタイプのゲームが生まれる余地があるとして期待しています。